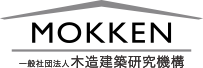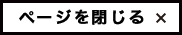2019.03.18
建築家からの問いかけにメーカー担当者が直接答える。 率直なやりとりの中から、建築材料の新たな可能性を探ります。
MOKKEN対談:建築家が問う建築材料の可能性 【 第1回 壁紙 】

建築家は自分の意図する建築を設計するために、構造材から仕上材、その原材料まで、慎重に吟味します。
建築家のニーズはどのあたりにあるのか。材料を選択する趣旨や目的に対して、現在市場に供給されているさまざまな材料は建築家の要望に
応えられているのだろうか。そんな疑問からこの企画を立ち上げました。
ここでは、現在第一線で活躍する建築家から率直に、建材に関するニーズや疑問、さらにはマニュアルにはない使用方法についてメーカーに問いかけていただきます。
それによって、素材自体が持つポテンシャルを最大限に引き出すことも可能ではないでしょうか。建築家にとっては既存材料利用方法のさらなる拡張に、
そしてメーカーにとっては新しい素材開発につなげられるのではないかと考えます。
第1回は室内の演出効果に重要な役割を果たす壁紙をテーマとしました。建築家が素材を選択する時に気を配るのは、機能や性能とともに、色彩や材質感がもたらす効果だからです。
取り上げたのは日本エムテクス株式会社が供給する塗り壁シート「エッグウォール」。
問いかける建築家はMount Fuji Architectsを主宰する原田真宏さん、メーカーは日本エムテクス取締役の藤本直哉さんです。
「エッグウォール」の原材料
原田:僕は建築に使う素材は自然素材がいいと、いつも思っています。建築を使う人や暮らす人にとっては、空間性や機能性も大切ですが、健康や快適性がより重要だと考えています。原材料は何ですか?
藤本:卵の殻です。
日本では卵の殻が年間約250トンほど排出されています。そのうちの10%ほどが食品の製造工場からのもので、その殻をリユースして原料としています。
卵の殻は、以前からチョークや運動場で引く白線や土壌改良剤として再利用されてきましたが、私たちは卵の殻のもつ、1個あたり1万個以上ある「気孔」という微細な穴に着目しました。ご承知のように多孔質であることが透湿性や消臭効果に役立ちます。
これまでにも塗り壁の材料として火山灰やゼオライトなどの鉱物素材も使っていましたが、有機物であり、しかも多孔質な卵の殻にはこれらと同等の透湿性や消臭効果がある事がわかり、まさに「コロンブスの卵」的な発想の転機でした。そうして、塗り壁やタイル、塗料などの機能性内装材を開発し、主力商品の透湿壁紙を「エッグウォール」と名付けました。
原田:どの程度、卵の殻を使っているんですか?
藤本:商品毎に違いますが、エッグウォールでは㎡あたり60個分。同様に卵の殻を使ったタイルでは750個分ぐらい使用しております。
施工とメンテナンス
原田:施工事例としてはどのようなところで使われているのですか?
藤本:住宅ではある程度普及していますが、非住宅の分野にはこれから積極的に挑戦していこうと考えています。すでに「丸井デパート」や大阪の「あべのハルカス」のベビーサロンなどにもエッグウォールを使っていただいています。
その理由は、リユース製品であることを環境保護の面から評価していただいたり、自然素材であることを評価いただいたからで、小さいお子さんがいるような木造保育園や文化施設からの引き合いが増えています。また、その方面に関心のあるお施主さんや工務店さんからも喜んでいただいております。
原田:具体的な話ですが、施工性やメンテナンスについてはいかがですか?
藤本:一般的な壁紙を貼るのと同じです。ただ、ビニールクロスと比べると、紙系の壁紙はすべて同じですが、下地に接着するノリの乾きが早いので若干貼りにくいかも知れません。でも、施工業者からは慣れれば問題はないと言われました。
メンテナンスに関してですが、ひっかき傷や目隙きなどに対しては、簡単に補修できる卵殻チョークとタッチアップ材のセットを用意しています。さらに最近はエッグウォールの上から塗れる塗料「エッグペイント」をリリースしました。
これによりエッグウォールの持つ調湿性、消臭性を損なわずに塗り替える事が可能になり、汚れも目立たなくなります。さらには、本来ならば貼り替えた際に出る大量の既存クロスのゴミも一切排出せずに済みます。その意味でも環境に優しいと自負しています。
余談になりますが、ある賃貸管理業者から聞いた話では、賃貸系では原状回復義務があり、入居者が入れ替わるたびに内装も貼替えなければなりません。それが理由でビニールクロスの簡便性が選ばれているようですが、クロスの上から塗り直す事ができれば、工期も早く工費も安くなり、ゴミの廃棄費用もかからない上に性能も付加できる、さらに上から何回でも塗り重ねられると絶賛いただきました。
この様な形で壁紙も「貼り換えずに塗り替える」という仕組みとして定着させていければと考えております。
原田:下地は限定されるのですか?
藤本:とくに限定はありませんが、基本的には石膏ボードを下地として考えています。
コスト
原田:コスト的にはいかがですか?
藤本:塗り壁は予算的に敷居が高く、自然素材には興味があるがなかなか手が出せないお施主様が多くいらっしゃると、左官業の世界では聞いております。そこで、塗り壁屋が作った「塗り壁紙」として商品化したのが「エッグウォール」なのです。
透湿紙の上に卵の殻を直接塗り付ける塗り壁シートで、これを40mのロール状にしたものを現場へ届け、クロス屋さんに貼ってもらう事で従来の塗り壁の半額ほどで提供できるようになりました。
材料の単価としては、一般的なビニールクロスと比較すると多少高価になりますが、材工込みの価格でいえば十分に手の届く範囲だと思います。
意図する空間を表現する素材として
原田:僕は素材感のある材料が好きなんです。自然素材の宿命かもしれないけれど、汚れますね。でも、むしろ変わらないと気持ち悪い。年の取り方が美しい素材がいい。それを求めています。
建築は肌で感じるところがあります。だから大事なところは自然素材を使います。壁紙は使ったことがありません。とくにビニールクロスは、どうしても時間の経過と共にみすぼらしくなる。ビニールクロスに手が出ないのはそのせいです。
天然素材を使ったということが、計測値のデータとして示されるより、実体感としてわかる方がいいのですが、実際に空間を体験してそれが感じられますか?
藤本:ペットなどを飼っていると匂いの違いがわかるようです。また、あえてビニールクロスの部屋と自然素材の部屋を併設し、より体感できるように演出しているモデルハウスもあります。
原田:工業製品化された製品は、いくらテクスチャーがあるといっても、大きい空間に使うと質感が弱くなってしまうと感じています。例えばタイルなどは製造工程上、本来焼きムラが出るもので、それが良いところでもある。でも日本のタイルはとてつもない技術を使って、完全に均質なものを作ってしまう(笑)。
テクスチャーが見た目にわかり難いんですね。その意味でも大きい面積で質感を出せる素材が欲しい。メーカー側ではムラは欠陥だと思われているようだけど、むしろ僕は歓迎します。今は均質な材料で溢れているから、手に入れるのが難しい。ムラが出るような使い方はできますか?
藤本:塗り壁の場合、骨材や大鋸屑を混ぜることもあります。ある物件でほうじ茶を入れて攪拌したこともありました。そうすると淡い茶色から濃いところ、薄いところなど天然のムラが出て高評価をいただきました。お茶渋、ヒバの鉋屑などを混ぜたこともありました。
しかし私たちメーカーとしては、ムラが出ることはタブーでもあるんです。商品化するには勇気が要ります。
それでも素材自体は自信を持ってお勧めできるものなので、これをベースとして、建築家の方々や左官さんとのコラボで、さらに豊かな表情や素材感のある空間表現が実現できると確信しております。
建築家の方々にはぜひご協力いただき、よりよい商品作りに努めていきたいと考えていますので、今後ともよろしくお願いいたします。